住所
〒952-0106 新潟県佐渡市新穂瓜生屋492地図情報をLINEに送る
バス
南線 「新穂行政サービスセンター前」下車南線:時刻表
車
両津港から車で約20分100台(無料)
 佐渡市には、古くから「説経人形」「のろま人形」「文弥人形」の三つの人形芝居があり、いずれも国の重要無形民俗文化財に指定されています。
佐渡市には、古くから「説経人形」「のろま人形」「文弥人形」の三つの人形芝居があり、いずれも国の重要無形民俗文化財に指定されています。
その中で一番古い説経人形は、太夫による三味線の弾き語りの説経節に合わ一人遣いの人形で合戦ものや人情ものを演じるもので江戸時代中頃まで江戸や上方などの都市で人気を呈しましたが、次第に中央から姿を消し、地方の大衆娯楽として演じられてきました。
現在、佐渡では唯一、廣栄座が継承しています。
 一方、のろま人形は、説経人形の幕間狂言として演じられてきました。一人遣いの突っ込み人形をあやつる遣い手が語る佐渡弁の巧みなセリフ回しで、時事ネタや風刺なども交えながらその場の雰囲気に合わせ話を展開し観衆の笑いを誘います。
一方、のろま人形は、説経人形の幕間狂言として演じられてきました。一人遣いの突っ込み人形をあやつる遣い手が語る佐渡弁の巧みなセリフ回しで、時事ネタや風刺なども交えながらその場の雰囲気に合わせ話を展開し観衆の笑いを誘います。
舞台は客席と舞台をおよそ1.5mの高い腰幕一枚で隔てただけの原始的なものを使います。
のろま人形に登場するのは、道化役の木の助を主人公に、下の長者、お花、仏師で、演目は「生地蔵」、「そば畑」、「五輪仏」など喜劇性の強いものが中心です。
 どの話も最後に決まって失敗した木の助が着物を脱がされ裸になり、放尿し大爆笑の中に幕となります。
どの話も最後に決まって失敗した木の助が着物を脱がされ裸になり、放尿し大爆笑の中に幕となります。
この木の助の放尿をあびると子宝に恵まれるとも言われています。
かつては、人形ごとに、人形株という所有権があって、それを持っていないと演じることはできませんでした。
◆のろま人形の上演について
のろま人形芝居が見られるのは、7月下旬から8月中旬の週末にかけて行われる「のろま人形上演会」、会場は佐渡市新穂地区の新穂公民館です。
この他、8月上旬に行われる佐渡市下新穂の新穂城址はすまつりでも上演されます。

登場人物の人形が佐渡弁で時にアドリブを入れながら話すところが楽しい。
最後に丸裸にされた主人公が、客席に向かって放尿するシーンがシャッターチャンス。
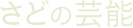

浜河内まつりの鬼太鼓
二人の鬼が向かい合って舞う前浜型鬼太鼓。門付けでは、各家でお花(ご祝儀)がいくつも出され、その数だけリクエストに応じて、多様な鬼の組み合わせで舞う。大獅子に頭をかんでもらうと一年健康に過ごせるという。

中興まつりの鬼太鼓と流鏑馬
中興集落内の3つの地域からそれぞれ鬼太鼓が出て各家を門付け。それらが夕方に中興神社に集まり競演するところが見どころで、正式な舞が見られる。子どもは、鬼に頭をなでてもらうと一年、健康過ごせるとか。

北川内まつりの小獅子舞
例祭の宵宮だけに奉納される小獅子舞。境内に特設された土俵で、白装束に鳥の羽根や色紙の房で飾られた鹿の頭をかぶり、腰に太鼓をつけた三匹獅子が静かに舞う。途中、つぶろという仮面男がからかいに入り舞う。