住所
〒952-0312 新潟県佐渡市吉岡793-1地図情報をLINEに送る
バス
南線 「竹田橋」下車南線:時刻表
 鷺流狂言は大蔵流・和泉流とともに狂言の三大流派として知られ、江戸時代に隆盛を迎えましたが、明治初期に宗家が廃絶し、大正時代初期には中央の狂言界から姿を消しました。
鷺流狂言は大蔵流・和泉流とともに狂言の三大流派として知られ、江戸時代に隆盛を迎えましたが、明治初期に宗家が廃絶し、大正時代初期には中央の狂言界から姿を消しました。
このため、現在もこの鷺流を伝承している地域は新潟県佐渡市・山口県山口市・佐賀県千代田町の3地区のみです。佐渡の鷺流は江戸時代後期に新穂潟上の葉梨源内が広め、幕末に来島した三河静観や明治時代に旧真野町の鶴間兵蔵らが興隆させたと伝わっています。
 その後、後継者が減少し、昭和30年代に消滅したと思われましたが、昭和50年代に旧真野町で伝承者が発見されたことにより再興され、昭和56年(1981)には保存団体の「佐渡鷺流狂言研究会」が発足し、後継者育成事業と狂言本の翻訳・研究活動が開始されました。昭和59年(1984)には新潟県の無形文化財に指定されています。
その後、後継者が減少し、昭和30年代に消滅したと思われましたが、昭和50年代に旧真野町で伝承者が発見されたことにより再興され、昭和56年(1981)には保存団体の「佐渡鷺流狂言研究会」が発足し、後継者育成事業と狂言本の翻訳・研究活動が開始されました。昭和59年(1984)には新潟県の無形文化財に指定されています。
現在、鷺流狂言は、佐渡の神社の祭りや演能の際に保存会のメンバーによって演じられています。
また、佐渡市の有形文化財として狂言本(10冊)があります。これは、明治時代に鷺流狂言師の三河静観所蔵の狂言本を、弟子の安藤世彦・安藤幸彦が筆写したものとされています。

狂言は喜劇的で庶民的なものと言われ能に比べ初めての人でもわかりやすい。役者の口調や表情、しぐさなどによって、おもしろおかしく話を展開し楽しめる。
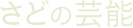

相川まつりの御太鼓
佐渡金銀山で栄えた旧相川町の7つの集落の例祭で、大工町の太鼓組の御太鼓が登場する。太鼓組は裏太鼓、豆まきの翁、長刀、棒、七つ役、提灯で構成され、烏帽子をかぶった豆まきの翁は、升と柿を持って舞う。

徳和まつり(春)
鬼太鼓は相川鉱山の抗夫が金を掘る姿を舞に取り入れたのが特徴で、オスメスの鬼が薙刀やバチを持ち片足をあげて舞う。「木遣り」が10番まで唄われる中、大獅子が時間をかけて石段を上る様は見応えがある。

北田野浦まつり
動物に仮装したものが太鼓などで囃子ながら中で踊り(しし舞)、その外側を「花笠」踊りが取り巻く。獅子頭は、竹の骨組みに苔を貼り、頭の毛にスガモという海藻を使う。薄明りの下で行われる幻想的な芸能。