住所
新潟県佐渡市水津553地図情報をLINEに送る
バス
東海岸線 「水津」下車 徒歩5分東海岸線:時刻表
 水津集落の白山神社の例祭の宵宮と本祭りで鬼太鼓が奉納されたあと集落内を一日かけて門付けします。
水津集落の白山神社の例祭の宵宮と本祭りで鬼太鼓が奉納されたあと集落内を一日かけて門付けします。
昭和23年に始まった鬼太鼓は、新穂潟上から習ったとされる「潟上型」で独自性を出すためその後、鬼の舞や太鼓のリズムもアレンジされています。
男鬼、女鬼の衣装は当初は、地元の人の手作りでした。
運営は、地元青年会の水津水生会鬼組が行っています。日本が高度成長期に入ると若者が島の外に働きに出るようになり
昭和38年から53年まで鬼太鼓は休止になりました。
 獅子舞(一対)は昭和25年から始まり門付けも行われましたが、人手不足のため現在は行われていません。
獅子舞(一対)は昭和25年から始まり門付けも行われましたが、人手不足のため現在は行われていません。
鬼太鼓は、集落の若手の交流の場にもなっていて、近年は、集落内にある駐在所の警察官も鬼として舞うようになりました。
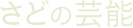

春駒
豊作や大漁を願う予祝として正月に門付けを行う芸能。かつては全国で行われていたが、現在はわずか数ヶ所に。木製の馬の首型を腰につけ馬にまたがったような形で舞う男春駒と、馬の首を手に持って舞う女春駒がある。

加茂歌代まつりの鬼太鼓
上組、中組、下組の3組の鬼太鼓が賑やかに門付けしてまわる。鬼太鼓の舞いは、両津夷集落から習ってきたものとされ、動きが大きい。朝6時に神社でそろって舞を奉納したあと、日が暮れるまで門付けを続ける。

天王まつりの鬼太鼓
この集落の鬼太鼓は、江戸時代に能太夫が鬼舞に能の動きを取り入れた振り付けで、牛尾神社に奉納したとされている。この振り付けは、佐渡の鬼太鼓の6割が取り入れている「潟上型」の始まりとされている。