住所
〒952-0302 新潟県佐渡市竹田562地図情報をLINEに送る
バス
南線 「竹田橋」下車南線:時刻表
 佐渡市真野地区竹田集落の大膳神社境内にある能舞台は、茅葺き、寄棟造で、1846年(弘化2年)に再建されたもので、佐渡に現存する能舞台の中で最も古いものです。
佐渡市真野地区竹田集落の大膳神社境内にある能舞台は、茅葺き、寄棟造で、1846年(弘化2年)に再建されたもので、佐渡に現存する能舞台の中で最も古いものです。
佐渡の能舞台のほとんどが雨風を避けるため戸が建てられていますが、ここは年中、開けられていて舞台正面の老松に太陽が描かれた珍しい鏡板が目を引きます。
佐渡には室町時代、1434年に能の大成者・世阿弥が流されていますが、世阿弥が島民に能を教えたという記録はありません。能が佐渡の人びとの間に普及したのは江戸時代以降のことです。
佐渡金銀山の発見により、1603年佐渡代官となった大久保長安が能楽師を連れてきたことに始まります。
 大正時代に佐渡を訪れた歌人、大町桂月が、「鶯や 十戸の村の 能舞台」と詠んだように、わずか十戸ばかりしかない農村集落にも能舞台があって、謡いや仕舞いをしたり、鼓を打ったりして楽しむ百姓が多くいるということへの驚きが記されています。
大正時代に佐渡を訪れた歌人、大町桂月が、「鶯や 十戸の村の 能舞台」と詠んだように、わずか十戸ばかりしかない農村集落にも能舞台があって、謡いや仕舞いをしたり、鼓を打ったりして楽しむ百姓が多くいるということへの驚きが記されています。
ここ大膳神社の例祭は毎年4月18日で、この日には神前に奉納する能が演じられる習わしになっています。このように祭りなど決められた日に能を披くことを定能といいます。
また佐渡に能の広がるきっかけとなった国仲の4つの能舞台を「国仲四ヶ所の御能場」とよび、大膳神社もそのひとつになっています。
 能楽協会のシテ方には観世流、金剛流、金春流、喜多流、宝生流の五流派ありますが、江戸時代、佐渡で主流となったのは観世流と宝生流です。現在、佐渡の人が務める演能のシテ方は全て宝生流となっています。
能楽協会のシテ方には観世流、金剛流、金春流、喜多流、宝生流の五流派ありますが、江戸時代、佐渡で主流となったのは観世流と宝生流です。現在、佐渡の人が務める演能のシテ方は全て宝生流となっています。
また、佐渡で能に携わる人たちの多くはプロではなく、それぞれ仕事をしながら能の研鑽に努めています。大膳神社の定能は、そんな能楽グループのひとつ真野能楽会により披かれていて、静寂の中に作り出される幽玄の世界は見る人の感動を誘います。
 なお、大膳神社能舞台では6月上旬に観光用に薪能も行われています。
なお、大膳神社能舞台では6月上旬に観光用に薪能も行われています。
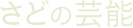

住吉まつりの鬼太鼓と樽囃子
50年前に地元の有志により始められた住吉の鬼太鼓は潟上型。子供から大人までが参加し、港町らしい荒々しい動きが特徴。近年は、女性による樽囃子が披露される。息のそろった高速打ちが見どころ。

小木町上野の大々神楽
京都から習ったと言われ、大々神楽と呼ばれる。獅子の他、警固と呼ばれる「ささら」と「銭太鼓」、そして「つぶろ」と演奏の太鼓と横笛で構成。

徳和まつり(秋)の鬼太鼓と大獅子
徳和集落の8つの集落で行う秋のまつりで、浅生集落から鬼太鼓、他の集落から大獅子が出る。鬼太鼓は、片足を上げて踊る「一足型」が特徴。江戸時代末期に伝わり、鉱山の坑夫が金を掘る姿を舞踊化したともいわれる。