住所
〒952-2222 新潟県佐渡市北川内1020地図情報をLINEに送る
バス
海府線 「北川内」下車 徒歩10分海府線:時刻表
 4月15日に行われる佐渡市北川内集落の熊野神社の例祭の前夜、宵宮に獅子舞いが奉納されます。この集落の獅子舞いは、明治の初めころに集落の人が赤泊地区から習ってきたと言われていますが、衣装や舞い方も違っています。舞いは、境内に俵とおがくずを使って作られた土俵の中で行われます。獅子は、雄獅子、中獅子、雌獅子の3匹で、脇役として「つぶろ」が加わります。獅子は白装束で、鳥の羽根や色紙の房で飾られた鹿の頭をかぶり、腰に太鼓をつけます。つぶろは面をかぶり、色紙の房で飾られたふり棒を持っています。
4月15日に行われる佐渡市北川内集落の熊野神社の例祭の前夜、宵宮に獅子舞いが奉納されます。この集落の獅子舞いは、明治の初めころに集落の人が赤泊地区から習ってきたと言われていますが、衣装や舞い方も違っています。舞いは、境内に俵とおがくずを使って作られた土俵の中で行われます。獅子は、雄獅子、中獅子、雌獅子の3匹で、脇役として「つぶろ」が加わります。獅子は白装束で、鳥の羽根や色紙の房で飾られた鹿の頭をかぶり、腰に太鼓をつけます。つぶろは面をかぶり、色紙の房で飾られたふり棒を持っています。
 獅子の舞は、大きく5つに区切られていて歌い手の短歌や長唄にあわせて腰の太鼓を打ち鳴らしながら舞います。途中、雌獅子を巡っての争いがあり、負けた獅子は土俵の外に出されます。つぶろは、獅子の舞の区切りの度に登場して、笛の音に合わせて、棒を振り回しながらこっけいに舞います。
獅子の舞は、大きく5つに区切られていて歌い手の短歌や長唄にあわせて腰の太鼓を打ち鳴らしながら舞います。途中、雌獅子を巡っての争いがあり、負けた獅子は土俵の外に出されます。つぶろは、獅子の舞の区切りの度に登場して、笛の音に合わせて、棒を振り回しながらこっけいに舞います。
 この獅子舞の前後には豆まき翁の舞と長刀があります。豆まきは翌日の本祭で門付けも行われます。豆まき翁は、裏と表で打つ太鼓のリズムに合わせ右手に枡を持って舞います。
この獅子舞の前後には豆まき翁の舞と長刀があります。豆まきは翌日の本祭で門付けも行われます。豆まき翁は、裏と表で打つ太鼓のリズムに合わせ右手に枡を持って舞います。
翁が舞い終わると長刀を持った2人が長刀を振り切りかざします。
かつては、大倉まつりで奉納される「箱馬」に似た芸もあったそうです。

夜の神社で、静かに舞われる獅子舞は、風情があります。
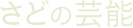

稲荷町の小獅子舞
桜の柄の幕の「雄じし」、鹿の角に紅葉の柄の幕の「雌じし」、鏡と鶴亀の柄の幕の「子じし」の三匹による踊り。しし頭の毛にはスガモと呼ばれる海草を泥で酸化させたものを使い、毛がよくなびくように椿油を塗る。

一ノ宮まつりの大獅子
10人ほどの男衆が入って各家を門付けしてまわる羽茂飯岡集落の大獅子。獅子は雌獅子だがやんちゃで、途中、家と家の間を移動する際、道路を使わず田んぼの中や川の中を渡る。大きく体をくねらせながら邪気を払う。

新町まつりのたかみ獅子
「たかみ」とは、竹や藤づるで編んだ農具(藤箕)。米などの穀物をふるい殻や塵を取り除く。「たかみ」を上下に重ねると獅子頭に見えることから作られたという。獅子には10人の男が入り威勢良く門付けしてまわる。